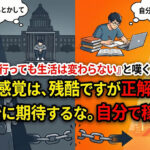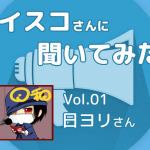先日、Youtubeのアベマプライムで「【核武装】『安上がり』参政党議員の発言が物議…保有コストの現実は?平和に核は必要か」というテーマが議論されていました。
広島育ち、広島県民の核武装論者である私も、この機会に日本の核保有について自分の考えを整理したいと思います。
「安上がり」発言とその問題点
まず、参政党・さや議員の「安上がり」発言についてです。
核武装には、開発コスト、維持コスト、施設や関連機器の改修コスト、さらに国際社会からの制裁による経済的損失など、膨大な負担が伴います。現状を考えると、これらをすべてクリアするのは非常に厳しいと言わざるを得ません。
現実の数字を見ても、「安上がり」という言葉には疑問を持ちます。2024年、核保有国9カ国の核関連支出は1,002億ドル(前年比+11%)に達し、そのうち米国が568億ドルを占めています(Reuters: Global nuclear arms spending up 11% in 2024, campaign group says)。
世界全体では毎秒3,169ドル、1分で約19万ドルが核兵器に費やされており、この金額はワクチンや住宅建設、インフラ整備など人道的事業に転用可能な規模です(ICAN:Get the Facts – Nuclear Spending Week of Action)。
ただ、比較対象を何に置くかで安上がりという言葉の持つ意味が変わってはきます。しかしそれでも「安上がり」と表現するのは安直すぎると言わざるを得ないです。
特に、現在の日本が「核武装します」と宣言すれば、中国や北朝鮮などは激しい反発を示し、最悪の場合「先制的な自衛攻撃」を名目に軍事行動に出る可能性もあります。米軍によるイラン核関連施設に対するGBU-57等のバンカーバスターで攻撃。これが示すのは、核開発を巡る“予防的/阻止的打撃”が現実的オプションとなり得るという厳しい実例です。ウクライナのNATO加盟を阻止するために侵攻したロシアの例からも、そういったリスクは無視できません。
こうした現実を踏まえると、「安上がりだから核を持つ」という発想は浅はかだと言わざるを得ません。おそらく真意としては、国民へのインパクトを重視した短い言葉選びだったのでしょうが、それでも国会議員(もしくはそれを目指す人)が発するにはあまりにも軽率な表現です。核保有を「コストの安さ」で語るのは、テロ国家や小国の独裁政権の発想に近く、日本が掲げるべき理念ではありません。
ちなみに、日本が「核武装します」と宣言することは容易くありません。それについて説明します。おそらくこの説明を聞いたら「核武装って絶対無理じゃん…」ってレベルです。
まず NPT(核拡散防止条約) の枠組みが最大の壁になります。日本はNPT上の 「非核兵器国(NNWS)」 であり、第II条(=第2条) で「核兵器を製造・取得しない」義務を負っています。したがって、NPTに加盟したまま自前で核を開発・保有することは条約違反 です。合法的に保有へ進むには、原則として 第X条(=第10条) にもとづく 「3か月前通告による脱退」 が前提になります。
第X条は、自国の至高の利益を脅かす「特別の出来事」を根拠に脱退できると定め、他の締約国と国連安保理への事前通告(3か月前)と理由の明示 を要求しています。北朝鮮は2003年に脱退を宣言 し、その後の核実験を経て 事実上の核保有国 となりました(※NPTが定義する“核兵器国”に該当したわけではありません)。いずれにせよ、政治・経済コストは極めて大きい 選択です。
「アメリカもNPT加盟国なのに核を持っているじゃないか」という疑問については、NPTの定義がカギです。NPTは“核兵器国(NWS)”を1967年1月1日以前に核爆発を行った5カ国(米・英・仏・露・中)に限定 しています。アメリカはこの 「認定された核兵器国」 として参加しているため保有自体はNPT違反ではありません。他方、日本は 非核兵器国 として参加しているため、締約国のまま自前保有へ進めば条約違反 になります。ちなみに核保有国であるインドやパキスタンはこの条約を不平等条約として加盟しませんでした。
加えて、CTBT(包括的核実験禁止条約)も日本は締結済みです。離脱は6か月通告+“至高の利益”理由が必要です。核を持っても実験なしで配備まで行く“無試験路線”は信頼性・運用面の政治的ハードルがさらに上がります。なので、これも離脱する必要があります。
さらに日米123協定(いわゆる「日米原子力協定」)も障壁になります。米国原子力法(AEA)123条に基づく二国間の「原子力の平和利用」協力の法的土台です。日本と米国の間で、移転される核物質・設備・技術は“平和目的に限る/核爆発装置に使わない/軍事目的に使わない”などを明文化されています。さらにIAEAによる保障措置(査察)の適用や物品返還・協力停止の権利が組み込まれています。
つまり、日本が条約内で核兵器化を図れば協定違反、NPT離脱後でも協力停止・返還が発動し得るため、燃料・技術・部材の流れが止まる構造です。
さらに国内法でも、原子力基本法第2条 が「核エネルギーの研究・開発・利用は平和目的に限定」と明記し、長年の国家方針である 「非核三原則(持たず・作らず・持ち込ませず)」 も存在します(※法的拘束力はないが強固な政策慣行)。
つまり、日本が核保有へ向かうには、条約・国内法・政策慣行という三重のハードル を越える必要があります。ここにあるのは、単なる“安上がり/高い”の物差しでは測れない巨大な政治・法・外交コスト です。
もはや核兵器以上の兵器を作るほうが良いのでは?と思うレベルです。
もちろん北朝鮮のように脱退することは可能かもしれませんが、とんでもない経済的打撃を受けるでしょう。現状でも「手取りがー!」「消費税がー!」なんて言っているような状態です。今より数倍景気が悪くなる覚悟を国民が持てるとは思えません。
核保有の条件 ― 「日本のため」だけでは足りない
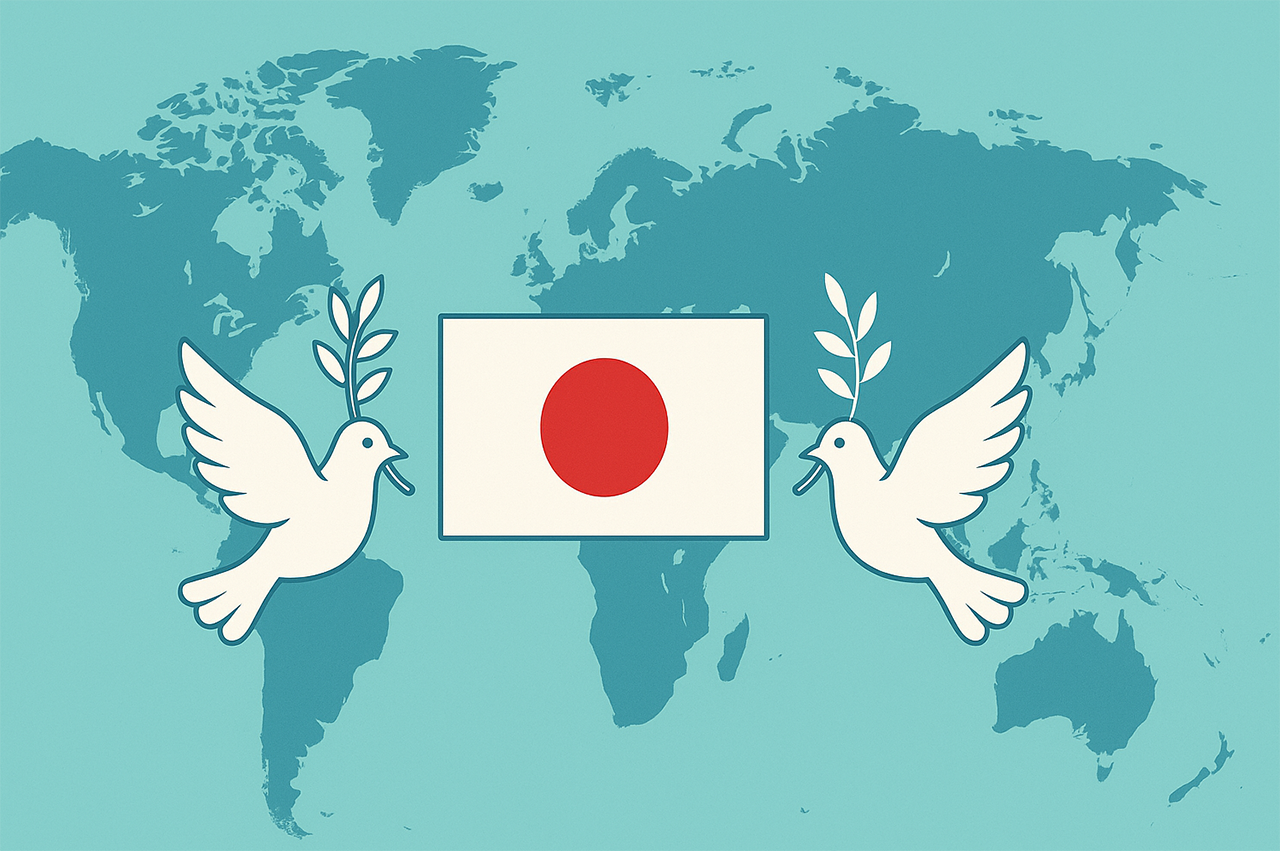
では、どのような理由や状況であれば核保有は正当化できるのか。それは、日本が核を持つことが世界やアジアにとっても価値があると認められる状況をつくることです。
中国や北朝鮮のような非民主的かつ核保有国が存在する中で、日本が民主主義陣営の抑止力として核を持つことは、国際的なバランスを取る上で意味を持ちます。米国を含め、他国が「日本が核を持つことは地域安定に資する」と判断するような環境づくりが不可欠です。
逆に、日本が自国防衛だけを理由に核保有へ踏み切れば、「ならば我々も自衛のために核を持つ」と主張する国が続出し、制御不能な核拡散を招きかねません。これは世界的な安全保障の悪化を意味します。
日本はODA(政府開発援助)を通じて多くの国に貢献してきました。今もしています。日本のおかげでインフラが整い、人命が救われた国々にとって、日本は不可欠な存在です。「日本が日本を守ることは世界にとって良いことだ」という信頼を築くことこそ、核保有の国際的な理解を得る土台になります。
「高ければ持たないのか?」という逆説
「安上がり」発言を逆に問えば、「高ければ持たないのか?」という話になります。安いから持つ、高いから持たないという判断軸は、国家安全保障の本質から外れています。核は、コストの多寡ではなく「必要だから持つ」ものです。
なぜ必要なのか。それは、国家にはあらゆるシナリオに対応できるカードを用意しておく責任があるからです。核はほぼ使用できない兵器であり、日本の歴史的背景からして実戦使用は極めて難しいでしょう。そもそも実戦使用するべきではないです。しかし「その状況が訪れた時に準備していない」というのは国家の怠慢です。
ゆえに、使わないことを前提としても保有しておく意義はあります。それが国家の責任です。
ちなみに、米国の核戦力維持・近代化には2025〜2034年の10年間で9,460億ドル(約143兆円)が見込まれており(米議会予算局:Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2025 to 2034)、英国のトライデント更新計画でも31 billionポンド(約3.9兆円)という巨額が投じられています(Wikipedia:Trident (UK nuclear programme))。日本が同規模の抑止体制を構築すれば、防衛費全体に匹敵する負担となる可能性があります。
核使用が極めて難しい理由 ― 「ロシアのロジック」との対比

ウクライナが実戦使用可能な核を保有していればロシアから攻められなかったという話しを聞きますが、果たしてそうでしょうか?核は核抑止には使えても戦争抑止にはそこまでの効力を発揮できない兵器です。なぜなら戦争には通常兵器の使用のみがルールとして適用されるためです。
そう、戦争にはルールがあるんです。戦争であってもルールを守る、もっと言うなら「守っている」と世界に言い訳できる必要があるんです。「この戦争は正当な理由に則り、致し方なくやっているんだ」と。
ロシアはウクライナ侵攻に際し、次のようなロジックを掲げました。
- ドンバス地域のロシア語話者が虐待やジェノサイドにさらされているため保護する
- ウクライナが「ネオナチ政権」に支配されており、これを除去する必要がある
- NATOの軍事インフラ拡大や武器供与がロシアの安全保障を直接脅かす
- 国連憲章第51条(自衛の権利)を根拠に軍事介入は法的にも正当
- ウクライナ国の存在を歴史的に否定し、「ロシアとウクライナは一つの民族」という文化的主張
これらは国際的に受け入れがたい理由ですが、ロシアとしては「自国防衛」という名目を立て、宣戦布告し軍事行動を正当化しました。もちろん民間人被害はありますが、コラテラルダメージの範疇として言い訳可能な形を保っています。米国がイラン核施設をバンカーバスターで精密攻撃した事例も、この枠組みに近いでしょう。
しかし、核兵器の使用はこれとは根本的に異なります。核は確実に数十万単位の民間人を巻き込み、数十年にわたる放射能汚染を引き起こします。侵略された側であっても、軽々に使うことは国際社会が許しません。
仮に核攻撃を行う場合、その兵器の性質上、事前警告が必要でしょう。IHLは”可能な場合、効果的な事前警告”を義務づける(追加議定書I・第57条)とあり、核兵器は本質的に無差別性・過度の被害の懸念が強く、適法な使用の想定自体が著しく困難です。しかし事前警告をすれば攻撃前に世界中から包囲され、最悪の場合、先に核報復を受ける可能性すらあります。
逆に警告なしに行えば、ただの大量虐殺です。これは戦争のルールを逸脱しロシアより悪い立場になります。世界からも「侵略された国とはいえ、本当に他に手段はなかったのか」「ロシアは最低限のルールを守っていた」と永遠に非難されるでしょう。国が主導して民間人を虐殺するという行為はそこまでに重いものなのです。
では第二次世界大戦のアメリカによる核攻撃はどうなんだ、という話しになりますが、当然許されるものではありません。ただ、戦勝国であるということ、そして、世の中が核兵器を知らなかったあの頃と今とでは状況が違いすぎるというわけです。
つまり、核兵器はロシアのように「自国なりのロジックを掲げて戦争する」という枠組みすら適用できない、極めて使用困難な兵器です。つまり核攻撃を抑止するためだけの戦略兵器です。それでも国家は、あらゆる事態に備えるためにこのカードを持っておく必要があります。
国際的に通用する核保有のロジック
ここまで内容を読んで分かる通り、もし日本が核を保有するなら、国際的に納得されるロジックが必要です。例えば、「世界唯一の被爆国かつ戦争を放棄した国が核抑止の役割を担い、最終的には核廃絶を実現する」という道筋です。最後に核を手放す国として、日本が核兵器廃絶のゴールを象徴する存在になる。そのために一時的に核を持つ、という大義です。私程度の頭ではこんな事くらいしか思いつきませんが、とにかく世界が納得する理由が必要なわけです。
間違っても「安上がりだから持つ」では、賛同する外国はほぼ存在しないでしょう。
何度もいいますが、核保有は、世界の安定に資するという正当性が必要不可欠です。
最後に
冒頭に申し上げた通り、私は日本の核武装は必要だと考えています。
それは、国家の統治能力でしか近づけない目標です。「安上がり」などと軽く語る政治では到底届かないでしょう。
日本の核武装論は、条約・同盟・国内合意という三重の条件をクリアしなければなりません。正直、これまで説明したとおり、核武装論者の私から見ても日本の核武装は条約などで雁字搦めなのこの状態から見るに、ほぼ不可能だと思っています。
だから今現実にやるべきは、拡大抑止の実効化(透明性・即応性・共同訓練)、通常抑止の層厚化(IAMD(多層防空)/ISR(常時警戒・監視)/C2(指揮統制)の底上げ)、そして国内合意の設計です。
つまり、敵国から日本が核攻撃をされたら確実に米国が相手の敵地を核攻撃してくれるという約束を取り付けること(そのレベルの強度な日米同盟の実現)。それからIAMD(多層防空)による敵国が核ミサイルを撃っても相当な確率で撃墜できるという能力を保有することです。
核の抑止とは原則として相手国に対して「核攻撃行うメリットがない」と思わせることです。
例えばあなたが日本に核ミサイルを10発撃つとします。その10発全てが日本の防空システムを掻い潜り、日本本土に命中する確率が40%だとします。加えてあなたが核ミサイルを発射したことよってアメリカから核の報復が実行される可能性が90%だったとします。この状況であなたは日本に対して核を撃とうと思いますか?まともな人なら撃ちません。撃つほうが損だからです。日本が核武装するよりも、こういった努力のほうが核攻撃の抑止力として遥かに現実的です。
日本の核武装は理想であり、その理想は追い求めますが、現実にも対処しなければならないため、現状の努力を続けていく他ないというわけです。そしてその努力を現在の日本はやっていると私は理解しています。いますが、「核武装をしよう!なぜなら安上がりだから!」なんて議員がいることは残念でしかたありません。
<参考リンク・出典>
- Reuters – Global nuclear arms spending up 11% in 2024
- ICAN – Nuclear Spending: Get the Facts
- 米議会予算局 (CBO) – Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2025 to 2034
- Wikipedia – Trident (UK nuclear programme)
- Wikipedia – Manhattan Project