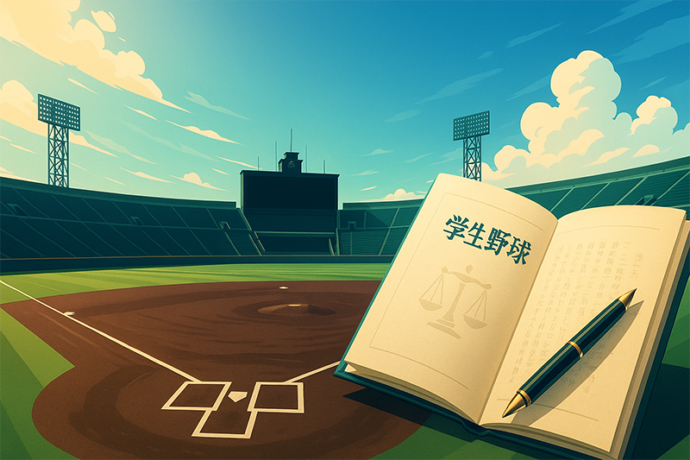高校野球において史上初めてのことが起こりました。それが良いことなら歓迎すべきことなのですが、残念ながら悪しきことです。
それは夏の全国高校野球 広陵が大会中に出場辞退という事件です。この件について今回は私の視点で語っていこうと思います。
まず、大前提として「いじめは絶対に駄目」です。
その上で、今回の問題をできるだけ俯瞰的に中立的見ていく努力をします。
この事件は第三者委員と警察により調査の途中です。またこの記事を書いているのは2025/8/21だということを考慮してください。現時点で分かっている範疇で書いていきます。
要旨
- 今年(2025年)1月に寮内で上級生4人が下級生1人へ暴力。高野連は3月に学校へ厳重注意。6月に第三者委員会が設置され、恒常化や性加害など“拡張主張部分”は調査中。
- 8月10日、学校は誹謗中傷や寮への爆破予告など安全上の懸念により甲子園出場を辞退。大会本部は受理。8月21日、監督・部長の交代と秋季大会への出場方針を発表。
- 「確定前の一律差止め」を避ける原則は日本学生野球憲章第29条4項。一方、資格・登録違反が確定した場合は高校野球特別規則により不戦勝・没収・勝利取消など事後修正が可能。
現在わかっている事実は?

注意:私の調べた結果であることを考慮してください。
- 1月:寮で禁止のカップ麺を食べた下級生を当時2年の部員4人が個別に殴打等。日本高野連は3月に厳重注意。
- 6月:学校は第三者委員会を設置(被害側の主張に応じて事実関係の再検証に入る)。
- 8月10日:学校が出場辞退を申し入れ、大会本部が受理。
- 辞退理由(学校説明):誹謗中傷・安全上の懸念(寮への爆破予告等)により運営困難。
- 8月21日:監督・部長の交代と秋季大会出場方針。現1・2年生へのアンケートで「暴力・いじめなしを確認」との学校発表。
- 被害生徒が転校したことは報道されているが、強制かどうかなどの詳細は未公表
分かっている事実は今のところこれだけです。『いじめの恒常化』『多数加害』『性加害の有無』などは第三者委員会・警察の調査結果待ちとなっています。現在も様々な追加情報が出ていますが、それらは事実の裏付けが取れていません。第三者委員会・警察など、きちんとした調査機関からの発表を待ったほうが懸命だと思います。
どうするのが妥当だったのか? 法と規則の“筋”―推定無罪と大会規程の交点

今回、広陵は大会中に出場を辞退するという結果になりました。この理由として、学校は誹謗中傷や寮への爆破予告など安全上の懸念により甲子園出場を辞退し、大会本部はそれを受理したという流れです。この流れに納得いかない声も多く「そもそも出場するな」などの意見もありました。
では何故出場するに至ったのか、また大会本部からの出場停止ではなく、学校からの辞退になったのか?について考えていきます。
これを考えるためには「日本学生野球憲章」を参照する必要があります。
学生野球憲章の第29条4項に「本憲章の定めた手続により処分がなされるまでは、学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、本憲章に違反したことを理由とした不利益な扱いを受けない」とあります。
つまり事実確定前の一律な「出場差し止め」は原則避ける設計となっています。現在は第三者委員と警察による調査中の状況であり、確定前の状態です。この観点から行くと出場・試合継続の判断が妥当だったのかもしれません。
そして、憲章の背景を考えるに、処分の最終決定権を持つ日本学生野球協会(JSBA)の審査室から学校に対しての出場停止というのは発動しづらく、学校側からの辞退申出ということになったのかもしれません。
事実、今回は、誹謗中傷や爆破予告等の安全リスクという「外的要因」で学校が自発的に辞退。これは“処分”ではなく危機管理判断という別レイヤーでの対応となります。
つまり憲章の枠組み上、処分は“事実認定後に将来効”が原則なので、未確定段階で「大会出場そのものを差し止める」タイプの全体処分は出しづらい設計です(資格・登録違反が確定したケースは別枠で大会規程が動きます)。
そのため今回は、学校が“安全配慮・運営困難”を理由に自主的に辞退――という大会運営上の判断に落ち着いた、と理解するのが自然なのかもしれません。
また、未確定の事案そのものを辞退理由にすると“前例”を作るため、学校としても憲章の趣旨(確定前の不利益取扱い抑制)に抵触しない言い方を選んだ可能性もあります。
もし、出場しつつも何らかの対処をするなら、事実確定前のためチーム全体の権利を守りつつ、関係個人にしぼった対外試合出場停止など、ピンポイントの暫定措置(連帯罰の抑制)で安全と公正を担保するのが妥当だと思います。
もしも重大不正が確からしいと判断したならば、規則上、不戦勝・没収・失格等の手当てがあり(事後発覚でも勝利取り消しの枠組みが各規定に存在)、後から結果を修正できるため、やはり「事実確定前は出場、事実確定後に厳正対処」が理にかなっていると思われます。
「そうじゃない!これは出場停止にすべきなんだ!疑わしいなら最初から出すな!」としたいなら、それは学生野球憲章の条項を見直すべきです。
最後に
「いじめ」という問題は「いじめられている側の発言は絶対に正しく、体制側やいじめているとされる側の発言は絶対に間違っている」とされがちです。それは私も理解できます。感情論ではそうです。今回も世間から出る様々な情報に真偽が問われることなく、噂や批判は苛烈しています。いじめの被害者側には十分寄り添うことはとても大切ではありますが、それと同時に冷静に中立的に判断していくことも重要です。
私の結論としては、被害申告の真偽やいじめの恒常化の有無については第三者委員と警察の結論で線を引き、それまでの対処は個人単位の暫定措置で安全と公正を両立し、チームの出場は憲章規定に則り原則維持、資格違反が確定した時点でこれも規定に則り結果を修正——これが、法理と規程に沿った最も中立的で再現性のある対応だと考えます。
参考リンク・出典
法規・規程(一次資料)
- 日本学生野球憲章(最新版・PDF)
- 高校野球特別規則 2025(PDF)※第24条「参加者資格規程に抵触した場合」等
- 令和7年度 大会参加者資格規程(PDF)
- 各種内規トップ(JSBA)
- 「部員の憲章違反行為に対する注意・厳重注意、処分および指導・措置の運用内規」(PDF)
- 「部員の憲章違反行為と野球部への措置の運用内規」(PDF)
公式発表・大会関連
- 日本高等学校野球連盟トピックス:「第107回全国高校野球選手権大会 代表校の出場辞退について」
- TBS NEWS DIG:【発表全文】広陵が出場辞退「高校野球ファン…各方面のみなさまに深くお詫び」 学校法人が発表 被害受けた部員と保護者にも「重ねてお詫び」夏の甲子園大会
主要報道(事実経過の確認に有用)
- 朝日新聞「広陵高校野球部で部員間暴力、高野連が厳重注意 7日の初戦には出場」
- 朝日新聞(社説)「広陵高校辞退 暴力を根絶するために」※6月に第三者委員会設置の記載あり
- 朝日新聞「広陵、高校野球選手権大会の出場辞退 『暴力の情報、重く受け止め』」
- 毎日新聞「夏の甲子園辞退の広陵 暴力発覚の1月から経緯を振り返る」
- 毎日新聞「暴行事案の舞台は『寮』、その功罪とは… 広陵、夏の甲子園辞退」
- 毎日新聞「退任の広陵・中井監督『責任感じている』 暴力事案で夏の辞退受け」
- テレ朝NEWS「広島・広陵高校 野球部員の不適切事案で謝罪(カップ麺・厳重注意・転校の説明)」
- 中国新聞(社説)「広陵高の甲子園大会辞退 暴力もネット中傷も許せぬ」※爆破予告などへの言及
- FNNプライムオンライン(テレビ新広島)「広陵高校野球部が“新体制”で秋の県大会出場へ…中井監督らの交代を発表」
- FNNプライムオンライン(テレビ新広島)「甲子園“出場辞退”から10日余り…広陵高校が中井監督の交代発表」
- RCC中国放送「〖広陵問題を振り返る〗中井哲之監督が交代…秋の公式戦は新体制で」